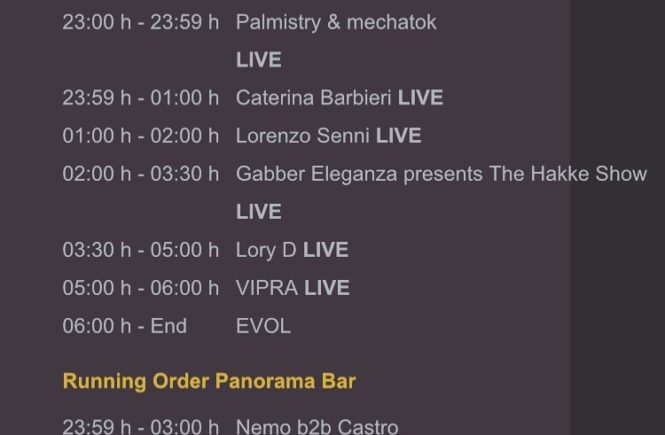1月の暮れから2月頭にかけて、CTM Festival 2019がベルリンで開催された。フェスティバル会期の10日間に渡って、数々のコンサート、クラブ・イベント、展示、ワークショップ、それからトーク・イベントが詰め込まれていた。
時間帯が重なるイベントも多く、全部行くなんて到底不可能な充実ぶりである。きっと参加者ひとり一人が異なる体験を、この「冒険的な音楽のための祭典」から得たはずだ。
私自身のCTMでの冒険は、フェス期間を終えてなお、東京の地から振り返ってこの記事を書いている今日までしばらく続くことになった。CTMで触れた音楽から得た印象が、疑問を投げかけ、ひらめきにつながって、新しいアーティストやパフォーマンス・スタイルに目を開かせてくれたからだ。
記憶に残る印象と、個人的にベルリンから東京へワープしてきたのも加わって、このレビューを単なるレビューではなくて、東京で起きている事と関連付けながら書くレビューにしよう、というアイディアが湧いた。結論から言えば、ベルリンと東京はそんなに遠くないぞ、というのと、東京もめっちゃアドベンチャラス。ということでした。
Contents of this Article
1月26日 // オープニング・コンサート: Rabih Beaini & Tarawangsawelas、Linn da Quebrada
開会式なのか前夜祭なのか、オープニング・コンサートというものが行われたのは、Hebbel am Ufer(通称HAU、訳すと水辺のへベル?川沿いに立地している)のHAU1という劇場。一番の番号が振られたHAU1は、三つあるHAUの会場の中で、建築的にも規模的にも一番大きくて、そしておそらく一番可愛らしい。
コンサートに先立ち、運営チームによる挨拶が。当初は小さなベルリンのスクワットで始まったこのフェスティバルが、20年も続けて来られたのは、たくさんの人々の努力と貢献があってこそ、とお礼の言葉を述べていた。今では、Festsaal Kreuzberg、Berghain、HAU、それからSchwuZクラブ(LGBTの解放のために貢献してきた40年の歴史を誇るベルリンのゲイ・クラブ)などにその開催場所を広げ、たくさんの人に愛されてきたフェスティバルなのである。私が会っただけでも、ドイツの外から毎年来てるという人に何人も出会ったので、この寒くて暗い時期のベルリンに来るだけの理由として愛されているのが良くわかる。






HAU2 impressions // Photo by Writer
この夜、二つのコンサートが用意されていた。最初にステージに上がったのは、Tarawangsawelas & Rabih Beaini (aka Morphosis)だった。タラワングサというスンダの伝統的なトランス音楽を現代解釈したものを演奏してくれた。
Tarawangsawelas & Rabih Beaini // Photo by Writer
右手の奏者の持っているバイオリンのような二弦の楽器は、それ自体がタラワングサと呼ばれる。そして左手の小さな琴のような楽器には七つの弦が張ってある。灯りの落ちた暗い劇場内を、ミニマルで反復的な音が重なり合う瞑想的な音楽が満たした。
休憩を挟んでステージ登場したのは、Linn da Quebradaというブラジルのクイアー・ラッパーだ。バンドとダンサーを引き連れ、マイクを持って歌うLinn da Quebradaに、一瞬で魅了される観客。クイアーとエロをひけびらかす遠慮容赦のないパフォーマンスに、ファンキ・カリオカ(日本ではバイレとも)濃厚なゲットー・グルーヴに総立ちで踊る。目を奪うパフォーマンスと、心をえぐるような歌詞の歌、すぐにこの人が好きになった。

Linn da Quebrada // Photo by Writer 
Linn da Quebrada // Photo by Writer
何曲かは英語の字幕が付いていたのでポルトガル語のわからない観客にも、彼女のリリックの無遠慮に挑発的な内容が掴めるという心遣いが。アナル・セックス、男性器、セックス・ワーク、そして愛についての歌詞だった。活動家としての彼女の思想をストレートに表現している、’Muhler‘という曲の歌詞を引用するとこんな感じ。「彼女はコック(男性器)が欲しいんじゃない、欲しいのは平和… 存在するために戦うトランスヴェスタイトに称賛を」
その頃、東京では… // 台湾のOrganik Festival 、日本でもスロー・ハウス旋風を巻き起こすVoodoohopコレクティヴ
Tarawangsawelas はこの初夏、台湾の Organik Festival 2019でも演奏をするので 、行ける人はお楽しみに。(さて、乗っけから東京じゃなくて台湾の話題ですが、近年このフェスに行く東京の友人や、日本からの出演者の多さから気になっていたフェスなのです。台湾まで3時間のフライトと時間的にも費用的にも、国内のフェスに行くのとそんなに変わらないじゃん、と気づき始めた人が多いのが年々日本からの参加者が増えている理由かも。)
Linn da Quebradaと並べて語れるような音楽性の日本のアーティストが思いつかなかったが、日本で今やカルト的な人気を誇るサン・パウロのVoodoohop について触れておきたい。Voodoohopが日本に来るきっかけを作ったのが、東京を拠点にしているdj 7eと彼女のパートナーだった。二人がブラジルに旅してこのカラフルなアート・コレクティブに出会い、一人また二人と日本に呼んでは日本のローカルDJやオーガナイザーに繋げて、小さいブッキングを重ねていった結果、日本各地でVoodoohop的なスロー・ハウスの音のパーティーがモコモコと溢れる旋風に。来日のたびにファンを増やしている。
Voodoohopの作る空間には、あらゆる性別や民族を抱擁するような、祝祭的なムードが漂っており、こうした空間を作る意識の根底にはLinn da Quebradaと同じく活動的な意味合いも読み取れる。それから、直接的な音楽の繋がりも少しあるようだ。VoodoohopのR Vincenzoが率いる即興集団’Roda de Sample’はこれまでの参加者の一人にLinn da Quebradaを挙げている。それからVoodoohopのCigarra はLinn da QuebradaのトラックSubmissa do 7º dia‘ をリミックスして曲を作ってる(以下で視聴可)。
1月28日 // As If We Were Solitary Selves: Lucy Railton、Thomas Ankersmit
続いてHAUでもう一夜。今度はHAU2。ここはかつてZodiak Free Arts Labというもはや伝説のクラブが、50年前に存在した場所でもある。Zodiakがあったのは1階部分で、今はレストラン・カフェとなっている。2階は当時も今も変わらず、劇場だ。
ここでThomas Ankersmit が “Perceptual Geography”というタイトルで立体音響の作品をサージ・モジュラーシンセを使って披露し、そしてその後チェロ奏者のLucy Railtonが彼女の新しいアルバム“Paradise 94” (Modern Loveから2018にリリース)に基づくエレクトロ・アコースティック・パフォーマンスを披露してくれるという事だった。

HAU2 Theater // Photo by Writer 
Lucy Railton “Paradice 94” Album Cover
Thomas Ankersmitは演奏を始める前に、音量について部分部分で激しい音や大きいところがあると注意を促した上で、そういう時は、入り口で配られたスポンジ耳栓ではなくて、自分の指などでその時々に応じて調整しながら聴くのが良いと説明してくれた。
この立体音響作品“Perceptual Geography”(上に埋め込んだsoundcloudでこの夜のパフォーマンスの一部が視聴できる)の聴体験は、なかなか凄かった。指向性の高い音域やテクスチャーを持つ音を多用して、メインに据える愛用楽器・サージのモジュラーシンセからは、まるで個体、粒のような音が吐き出される。頭を少しでも傾けると、音が劇的に変化する。作品のタイトルPerceptual Geography=知覚される地理 とは60年代に定義された理論で、地理とは心理的・文化的に知覚されて主観的に存在するというもの。そのタイトルの示す通り、各観客のこの作品の知覚体験は、文字通り各自の耳の傾け方によって様々だったはず。
続いて、Lucy Railtonがチェロとエレクトロニクスを使って彼女の2018年アルバム“Paradise 94” に基づくコンポジションを披露してくれた。この数日前に、彼女はベルリンにできた小さな音楽バー、KM28でミニマル・ドローンの作曲で知られるPhill Niblockのコンポジションをチェロ一本で演奏していた。今夜また彼女を違った形で観ることができて、クラシック楽器がエレクトリニクスと組み合わさり入力ソースとなるのをまじまじと見ることが出来たのは面白かった。
その頃、東京では… Super Deluxeが惜しまれながら閉店、でもミニマル・ドローンはSoupで聴こう
Thomas Ankersmitが最後に日本公演を行ったのは2013年、Phill Niblockと共にSuper Deluxeのステージに立った時だ。そのさらに10年前に、この二人は同じくSuper Deluxeにて初共演をし、以来コラボレーションが続いてきたそうだ。
残念なことに、2019年の初旬にSuper Deluxeは、惜しまれながらその16年の歴史に一旦終止符を打った。東京で、実験的な音楽が聴ける数少ない大きなベニューで、これ儲かるの?的なイベントもたくさん演っていた不思議な箱だった。だけど、東京まだ大丈夫だな、と思えるのが落合Soupの存在!Super Deluxeに比べると箱の規模は小さいものの、音のクオリティー、実験的な音楽のブッキングセンスの評判は、遠くベルリンにも届いているほど。「え、東京から来たの?」と私がどこから来たか知るや否や「Soup知ってる?東京でいちばん好き!」と言われたことがしばしばあった。ミニマル、ドローン、インプロ、エレクトロ・アコースティックなどのコンサート(他にもいっぱい)が聴けるのはココ。
友達に勧めてもらい、とある日曜日の夜のイベントにおじゃました。Opt Gear #4というイベントだった。この日観た凄い人たちがstand alone-404だ。ノイズ・ポスト・ジャズとでも言おうか、マッドなキーボーディストの坂口光央、ドラマーの服部正嗣の変態数学的ビート、それからダブル・ベースでメロディーラインを奏でるジャジーな笠井トオルのトリオだ。いくつかyoutubeでビデオを見つけて後で見てみたけど、Soupでの音のパワーと衝撃はビデオでは伝えきれない。SoupのPAは何人かいるらしいのだが、彼らの大音量でのオペレーションの定評は高い。ミュージシャンからの信頼は厚く、音をネクスト・レベルに持ち上げてくれる。なので、Soupでレコーディングをするというバンドもいるらしい。実際、ここの箱の配置は、四隅のスピーカーが作る音響の中心点をステージの中心に持ってくるという変わった配置で、観客はどちらかというとステージのモニター音を見守りながら聴くという感じ。本当に素晴らしい音楽体験が出来て、大満足だった。次回から音楽耳栓持参で!
1月30日 // As if We Were Heard: 700 Bliss (Moor Mother & DJ Haram)、Cocaine Piss、Tim Tetzner、Caliph 8 & Nonplus
“No Photos in our Club please!!” (写真撮影はお断り!)
“Sorry, but not Today.” (今日は、ダメ。)
さて、この2つのフレーズから何の話だか検討がついた人は鋭い。今夜のコンサート会場は、ベルグハインでございます。(今日は、ってなんやねん。今日は入れてあげない、っていつも言われる。)
この夜も入り口にバウンサーが立っているのを見て驚いた。だって、夕方の時間帯のコンサートだし、フェスのプログラムの一環なのに、なぜバウンサーが。チケットを事前に買っていたにも関わらず、入り口でバウンサーに首を横に振られて、無駄に傷つく。前売り券を見せると、すんなり通してくれたものの、入り口で当日券を買うつもりで来た人たちは、しっかりと帰されている人がちらほら。(オンラインでもチケットは買えるので、チケット買ってから入っちゃいましょう。)
撮影禁止のポリシーに従い、写真は一切撮っていないので、この日のレビューについてはアーティストとバンド専属カメラマンのインスタから写真を紹介。(バンド専属カメラマンも写真撮影禁止されたって。)
まず一つ目のアクトは、パンクバンドの音源のサンプリングだけで作り上げるサウンドコラージュを披露したTim Tetznerだった。フロアの真ん中に置かれたパソコンを使って音を出すティムの周りに、立ったり、座ったり、囲んで見守る観客。面白いことに、サンプリング元のパンクの音源が70年代とか80年代の空気感満載なのだが、後でティムに聞くとほとんど最近のバンドばっかりで、いくつかは去年のリリースのものだけど、そう聴こえるから不思議だよね、と。
二番手はマニラ出身のCaliph8 + Nonplusのデュオだ。場所を変え前方のステージで演奏が始まったので転換は即時。ベースが重たく鳴ってるポリリズミックな音楽を、MPCサンプラーなどを使って演奏。アブストラクトなヒップホップ、テクノ、サウンド・コラージュ、ダビーな音がスピーカーを震わせ観客が踊り出す。
このクラブのフロアには、というか音響が良く出来たクラブのフロアには、前も後ろも横もないのだな、と次なるアクトが今度は右手に組まれたステージで演奏を始めた時に気付かされる。
Moor MotherとDj Haramによるユニット、 700 Blissだった。Moor Motherのことは以前に、彼女のフリー・ジャズ・プロジェクトIrreversible Entanglementsで観て以来、詩的な音楽性に感激して大好きなアーティストの一人なのだが、このDJ Haramがベース・ミュージックのトラックを担当する700 Blissはイズ・ザ・シット、見逃し厳禁である。ガスマスクを着けて登場したMoor Motherのラップの歌詞は真摯で、彼女の目を通して見る世界の矛盾や不穏をクレバーな言葉を使って、聞く人に投げかける、そして考えさせるのが上手い。差別主義的、物質主義的、政治の腐敗的、そして暴力に怯えて生きなければいけない現状は、受け入れたら終わりだぞという警告のメッセージ。彼女の言葉選びは、刃のように鋭いけれど、傲慢ではない。懐疑的だけど、諦めてはいない。ステージから降りると、彼女の小さな姿は人の海に飲み込まれ消えた。観客の顔を一人一人覗き込みながら、激しくラップする様子が垣間見える。イン・ユア・フェイスである。

続いて出てきたバンドは、稀に見るヒドイネーミングセンス。その名も Cocaine Piss。
「僕たちコカインなんかやらないんだよ!」ギタリストのマティアスが、笑いながら説明してくれた。「良く聞かれるんだけどね、何でって。考え得る限りのヒドイ名前を付けたかっただけで、いいじゃん、ってなって。バンド名のせいで、ブッキングを嫌がるプロモーターもたまにいるんだけど、大体皆んないずれ分かってくれて、嬉しいことにヨーロッパ各地のジャズ・フェスティバルからパンク・ベニューから、幅広いお客さんの前で演奏する機会に恵まれてる!」
個人的には、面白いバンドって小さいベニューから大きいとこまで演奏してて、ポップでもロックでもジャズでも構わず色んなフェスに呼ばれる音楽って素敵だな、と思う。このバンドの奇妙なパンク・サウンドは、どんな音楽ファンにとっても面白すぎる音だった。
ボーカルのAurélieの特徴的な声、ギタリストのMathiasのキレのあるリフとサイケなソロは、パンクの楽しさ全開。ドラマーのYannickはグラつかぬ安定感ながら、でも遊び心のあるふざけたフィルを多用。新しく加わったベーシストのFarida Amadouはフリー・インプロのシーンで活動していたベーシストで、このバンドに更なるフリーダムを持ち込んでいるのかも。パンク的な曲の構成の中で楽しく遊んでいるな、というのが彼らの音楽性。彼らのライブは、爆発しているんだけど、やってる本人たち凄くリラックスしていて、とにかく超楽しそう。生で観るのをオススメ!
Cocaine Pissは間も無くこの4月にSteve Albiniをレコーディング・エンジニアに迎えて新譜 “Passionate And Tragic“をリリース予定。そしてSteve Albini繋がりもあって…
その頃、東京では… OOIOO、GEZAN (Steve Albiniで彼らもリリース済み)、the hatch、Black Smokersを迎えて開催されたBODY ODDという主催者のイベントが面白い。
BODY ODD というイベントを知ってますか。ジャンルレスなこういうパーティーを、音楽好きな人は欲していたはず。不定期開催で7回目になるという、今回は渋谷のContactで行われたこのイベントに運良く遭遇。嬉しい。ハード・コア・パンク、ヒップホップ、実験音楽、レフトフィールドなダンスミュージックという組み合わせのこの夜が、CTMの1月30日の夜の記憶と被る。
日本は音楽シーンが色んなマイクロ・シーンに向かって狭小化しがちで、バンドは熱狂的な信者を集めてファンクラブみたいになりやすいし、djパーティーは友達同士の社交場になってしまうし、そんな毎回同じもの聴いたり観たりしてたらすぐにつまらなくなってしまう。何か観に行きたいと思っても、どこに行ったらいいか良くわからないし、チケット代も高いから慎重に選ばないといけない。その結果、確実に好きだし、楽しめると知ってるモノを自ずと選ぶことになるのが悩みだった。それから、演奏する側も、お客さんを満足させなきゃいけないという使命感が辛そう。エキスペリメンタルなジャズとかインプロですら、最後に奏者が全員出てきて大きい音出して、ほら〜!みたいなのしなきゃいけない雰囲気ってどうなんでしょうか。音楽性とか表現の自由が担保に取られている。
BODY ODDで観たバンドのうち、札幌のthe hatchという、トロンボーンをシャウトの代わりに吹くボーカリストを据えた、一風変わったジャズなハードコアパンクバンドのパフォーマンスが目を開かせてくれた。ハード・コアでアグレッシヴに荒れ狂う演奏したところで、最後の一曲をとてもメロウなピアノのインストで締め括ったのだった。こう終わる?と予想していなかった展開で、観客は少し呆気にとられていた様子だったが、バンドのジャジーな音楽性を印象付ける非常に美しいパフォーマンスだった。
もう一つ目を見開きながら観たのが、GEZANだ。彼らは2018年の10月にリリースしたアルバムが、先ほどCocaine Pissの項で触れた、レコーディングエンジニアのSteve Albiniのスタジオで録音されたということ。このバンドのボーカルのマヒ・トゥ・ザ・ピーポーのステージでの存在感は、youtubeでどんなにビデオを観ても生で伝わってくるものと差異があった。是非生で。
目が離せないボーカルといえば、Black SmokerのK-BOMBも触れずには居られない。K-BOMBはラッパーであり、ヴィジュアル&サウンド・アーティストであり、フリー・インプロヴァイザーであり、ゆるキャラでもある。彼の特有の声と言葉選びのセンスは、コミカルで、ただの擬音語じゃん、と思えば突如ウィット溢れる深みに転じる。日本語がわからなくても、彼のラップはジャズ・ボーカルとしても聞き応えがある。だから海外にも呼ばれて通じるのでしょうね、昨年のBerlin Atonalでもジャズ・ベーシストの鈴木OMA勲さんとKILLER-OMAとして出演していたのが記憶に新しい。
2月1日// As If We Were Strong: Setabuhan、Lightning Bolt
この頃、北アメリカ大陸をポーラー・ヴォルテックスの寒波が襲い、都市を氷責めにして、アメリカ北部の都市は交通機関が麻痺していた。一方でベルリンは、暖冬に恵まれ、のどかな冬の晴れた日を楽しんでいた。「ポーラー・ヴォルテックスの影響でフライトがキャンセルされたため、今夜のクラブ・ナイトでのVenetian Snaresの出演は中止となります」というフェスティバルによるアナウンスで、私は初めてこの自然の驚異について知った。まぁ、よい。がっかりしつつも、夕方のコンサート会場へ既に向かっていた。
夕方のコンサートはFestsaal Keruzbergという会場で、インドネシアのボーカリストRully Shabara率いるSetabuhanと、ニューヨークのフリーフォーム・ノイズ・ロック・デュオLightning Boltがステージを分かつ。
Rully ShabaraはSenyawaというネオ・トライバル・パンク・デュオのボーカリストとして知られる。今夜彼はSetabuhanというプロジェクトで、二人のドラマーと彼の声でトライバルなトランス・ミュージックを奏でた。パフォーマンスの一部として、格闘技の実演も行われ、音楽にドラマチックなストーリーとして脚色を加えた。この格闘技は、接触を禁じ、流れるような即興の動きで力と力の交換、生と死、共に生きてそして死ぬ「他」への敬意を表す芝居のようなものだった。
Setabuhan // Photo by writer Setabuhan // Photo by writer Lightning Bolt // Photo by writer
次に、Lightning Bolt が爆発的なハード・ノイズ・ロックを披露すると、ステージの前はモッシュ・ピットと化した。ギターのブライアンとドラムのブライアン。この類の音特有の過激性なエナジーは大好きだけど、モッシュの過激なエナジー交換は戴けない。モッシュに飛びこんで行ってしまうような方、あれは一体何なのか、説明してもらいたい。
その頃、東京では…内橋和久を東京で目撃
Rully ShabaraとSenyawaと共演している日本人ミュージシャンといえば、ギタリストでダクソフォン奏者の内橋和久がいらっしゃった。ダクソフォンとは、80年代に発明された主に木で出来た楽器で、エレキギターのように振動をピックアップで拾って電気に変える楽器だ。ダクソフォンの内橋和久を迎え彼らはMAHANYAWAとして2015年にアルバムをリリースしている。
この3月東京で、今はベルリンに拠点を置いているという内橋和久の演奏を観る機会に運良く恵まれた。渋谷公演通りクラシックスという店だった。この日、内橋さんはギターを弾いてくれたが、背筋を正して腕を組んで見たくなるような緊張感のある、凄いギタープレイだった。ベルリン拠点というものの、頻繁に日本はじめ世界各地で演奏している様子なのでお近くに内橋さんが来る際には観るべし。最新スケジュールはこちら。
2月2日 // Actress + Young Paint ~AIの妖精の世界初公開

Actress + Young Paint World Premier // Photo by Writer 
Actress + Young Paint World Premier // Photo by Writer
Actress + Young Paint はActressことDarren Cunninghamの新しいプロジェクトで、Young PaintとはActressの音楽の特徴を学習途上の人工知能とのこと。この夜はワールドプレミアとして、二人の即興的インタラクションが観られるという告知がなされていたのだが…。
このアクトを観た後から、大きなモヤモヤが湧いてしまった。そもそも、AIって何なのか。Actressが使っているプログラムは、本当にAIなのか?機械学習って何なのか、データを集めて統計するのとはどう違うのか。AIが音楽を作る、というのと、アルゴリズムを使ったコンピュータ・ミュージックとの違いとは?
AIと音楽の関係について調べ始めると収拾が付かなくなってきた。この分野で音楽を作っている色々なミュージシャンのアプローチを探る結果、この人に会うことに…
その頃、東京では… AlgoraveのRenick BellとKΣITOの即興
東京を拠点とする Renick Bell はAlgoraveのメンバーとして、エージェント方式というプログラミング方法を用いた自作ソフトウェアで、ライブコーディングによる演奏を行っている。コンピューターの歴史から始まり、これと表裏一体のAIの歴史、それから近年のAI技術への注目が集まる理由となった2012年頃の深層学習分野での技術革新について、調べれば調べるほど難しいコンピュータ界隈の話題にハマって行く。だけど、Renickに話を聞いてみたのは正解で、明快なヒントと方向性を与えてくれたので、彼に聞いた話を含め、他のアーティストのAIを使った製作など掘り下げて縦断的な記事をただいま執筆中です。
東京でのRenickのパフォーマンスは、MPC奏者の KΣITO と共に、ライブコーディングとパッドで叩き出されるリズムとの即興。神楽坂の神楽音という箱で、香港のAbsurd TRAXクルーからアクトをいくつか召喚して行われたこちらのイベントに出演していた。Conductiveと名付けられたRenickのエージェント方式ソフトウェアを使ったコードの海とKΣITOのMPCでのテクニックは、コンピューターを巧みに使いこなした音楽だった。
2月2日 // As If We Knew: Deena Abdelwahed、Fatima Al Qadiri他
フェミニンなアクトに焦点を当てた企画としてSchwuZクラブで開催されたこの夜のイベントには、などのFatima Al Qadiri、Linn da Quebradaそして Deena Abdelwahedなどの美しい異才の名前が並ぶ。
フェスのいいところって、普段行かないような会場やクラブを訪れ知るきっかけになるというところ。SchwuZクラブのことは、この時初めて知った。1977年に開業したこの歴史あるゲイ・クラブは、ベルリンでのゲイ達の市民運動の歴史を一緒に歩んできた場所だ。入り口に貼ってあった張り紙に感動した。この場所は、誰もが安全に楽しめるセーフ・スペースです、と10ヶ国語で十箇所に貼ってあるのだ。あらゆるハラスメントは禁止、何か身に危険を感じたらすぐにスタッフに言ってください、と、ここまでたくさんの言語ではっきり伝えるという姿勢に、とても感銘を受けた。

Entrance at SchwuZ // Photo by writer 
Signage at SchwuZ declaring a safe space // Photo by writer 
Deena Abdelwahed // Photo by writer
この夜のハイライトは、チュニジア人の歌手でトラック・プロデューサー/DJのDeena Abdelwahedだった。アラビア音楽をサンプリングしたテクノやレフト・フィールドなベース・ミュージックは、例えばShackletonとか、今まで聴いたことがあると思うが、彼女の音楽はそれをもっと推し進めて、アラビア音階やリズムを盛り込む。逆に、アバンギャルド・テクノやベースを、伝統的なアラビア音楽に取り入れたと言った方が正解だ。彼女の繰り出すトリッキーなビートで踊るのはとっても楽しく、戦争の音を思わせるサンプリングで悲痛なエモーションを描きつつも、彼女の美しいボーカルがそれを癒す。瞬く間に満員のSchwuZのフロアを虜にしていた。お気に入りの音楽ライター、Tom FarberがDeenaに行っているインタビューを見つけたので、その記事を一部抜粋する。
Abdelwahedは高級ホテルでジャズのカバーを歌うとこからキャリアを始めた。その後Flying LotusやJ Dillaといった、ファンクやヒップホップや電子音楽を横断するような音楽を作っているアーティストを発見することになった。だが、彼女が初めて、自分の音楽性としてしっくり来ると発見したのは、シカゴ・ジュークだった。シカゴ・ジュークと伝統的なアラブ音楽の共通点として、どちらもテンポの速い、正確なパーカッションに重点を置き、独自のダンス・スタイルを作り上げているというところ。そこにAbdelwahed は惹かれた。
https://www.residentadvisor.net/features/2990
Deenaがジューク・フットワークとアラビア音楽の間で見つけたビートの繋がりって、本当に面白い!音楽は世界を一つにするはず、耳を傾けることさえ忘れなければ。
その頃、東京では… Deena Abdelwahed が代官山Unitで開催される Frue にて日本デビュー
Deena Abdelwahedの日本初公演を企画したのが、日本のオーガナイザーFRUEのチーム。SvrecaとWata Igarashiと共に一夜を織り成す。FRUEはハイ・クオリティーなアクトを世界中から日本に呼んでくれている。妥協しないプロダクションへの姿勢とリスキーな企画で定評を集める彼らの、アンテナの感度と音楽愛は日本の中でもトップのクオリティー。
残念ながら、今回の来日でDeenaは東京での公演しか予定しておらず、Frueへの出演を終えるとすぐに拠点のヨーロッパに帰ってしまう。日本のシーンも、遠くのミュージシャンがもう少しツアーし易いと楽しくなると思うんですがね。渡航費などのプロダクション・コストを、公平に分けるシステムにイノベーションが起こせれば、絶対に解決できる問題だと思うのですが。みなさん、この可能性について、ちょっと話し合ってみませんか?
この記事で触れたアーティストのビデオをいくつか貼っておきます:)